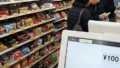いつも利用していたお店が気づけばなくなっていると、少し寂しい気持ちになりますよね。ローソンストア100の店舗数について調べているあなたは、まさにそんな変化を肌で感じているのかもしれません。過去からの推移や都道府県ごとの状況、あるいは店舗数が減った理由や閉店に関する情報を求めているのではないでしょうか。特に東京や大阪などのランキング上位地域にお住まいの方は、身近な店舗の行方が気になるところかと思います。この記事では、ローソンストア100が直面している現状や今後の戦略について、私なりに深掘りしてみようと思います。

- ローソンストア100が2030年に向けて店舗数を330店に集約する理由
- 最近店舗が減っている背景にある「まいばすけっと」など競合の影響
- 現在の店舗数が集中している都道府県やエリアの特性
- 客数や売上のデータから読み解く今後のコンビニ勢力図の変化
ローソンストア100の店舗数減少と現状の推移

まずは、私たちが気になっている「現在の店舗数」とその変化について見ていきましょう。最近、街中でローソンストア100を見かける頻度が変わったと感じることはありませんか?ここでは、過去から現在に至るまでの店舗数の流れや、どの地域に店舗が多いのかといった基本的なデータ、そしてなぜ減少傾向にあるのかという核心部分について整理してみます。
過去からの店舗数推移と減少トレンド
ローソンストア100の店舗数について調べてみると、実はここ数年で大きな変化が起きていることがわかります。正確な店舗数は日々変動しますが、一般的には約600店から700店前後で推移していると言われています。ただ、この数字は以前に比べると明らかに減少トレンドに入っているんですよね。
ローソングループ全体の月次データを見ても、新規出店よりも閉店の数が上回る「純減」の傾向が見られます。たとえば2025年3月のデータでは、グループ全体で34店舗の純減となっていました。これは、単に人気がなくなったという単純な話ではなく、企業として「筋肉質な経営」を目指して、採算の合わない店舗を整理している段階にあると考えられます。
ポイント
店舗数が減っているのは、無計画な撤退ではなく、将来を見据えた「構造改革」の一環である可能性が高いです。
都道府県別の店舗数分布と集中エリア
次に、ローソンストア100がどのあたりに多いのかを見てみましょう。皆さんの住んでいる地域にはありますか?実はローソンストア100は全国どこにでもあるわけではなく、特定のエリアにギュッと集中して出店しているのが特徴なんです。
具体的には、関東、中部、近畿の三大都市圏に店舗網が張り巡らされています。これは、100円均一の商品や生鮮食品を効率よく配送するための物流システムが関係しているみたいですね。逆に言うと、地方都市ではあまり見かけないレアなコンビニとも言えるかもしれません。
店舗数ランキング上位地域の特性
都道府県別の店舗数ランキングを見てみると、やはり人口の多い都市部が上位を占めています。特に店舗数が多いと推測されるのは以下の地域です。
- 東京都
- 神奈川県
- 大阪府
これらの地域は、一人暮らしの人や共働き世帯が多く、「コンビニの手軽さでスーパーのような食材が買える」というローソンストア100の強みが活きる場所でした。しかし、これらは同時に、他のコンビニやスーパーもひしめき合う「超激戦区」でもあります。
市場が飽和しているこのエリアでは、少しの環境変化が店舗の存続に大きく影響します。今起きている店舗整理も、まずはこれら大都市圏の競争が激しい場所から進んでいると考えられそうです。
店舗数が減った最大の理由と客数減
では、なぜこれほどまでに店舗数を減らす必要が出てきたのでしょうか。その最大の理由は、ズバリ「客数の減少」にあります。2025年3月の実績データを見ると、既存店の客数は前年比で94.6%まで落ち込んでいるんです。
お客さんが減った背景には、私たちの生活スタイルの変化や、より魅力的な選択肢が増えたことが挙げられます。「100円で何でも揃う」というモデルは画期的でしたが、最近は物価高の影響もあり、その優位性を維持するのが難しくなっているのかもしれません。
注意点
客数が減っているといっても、すべての店舗が暇になったわけではなく、一部の競合店にお客さんが流れているという構造的な問題があります。
競合まいばすけっとの店舗数との比較
ローソンストア100の客数を奪っている最大のライバルと言われているのが、イオンが展開する小型スーパー「まいばすけっと」です。このお店、最近ものすごい勢いで増えていますよね。
まいばすけっとは、コンビニと同じくらいの広さでありながら、価格はスーパー並みに安いというのが特徴です。店舗数はすでに1,200店を超えており、2030年には2,500店、将来的には5,000店を目指すという攻撃的な拡大戦略をとっています。
この「店舗数拡大中のまいばすけっと」と「店舗数縮小中のローソンストア100」という対照的な図式が、今の小売業界のリアルな姿を表している気がします。
| 比較項目 | ローソンストア100 | まいばすけっと(競合) |
|---|---|---|
| 今後の店舗数戦略 | 縮小・集約(330店へ) | 拡大(2500店以上へ) |
| 価格帯 | 100円均一+標準価格 | コンビニより数割安い |
| 強み | コンビニの利便性 | 圧倒的な低価格とPB商品 |
2030年に向けたローソンストア100の店舗数目標

現状の減少トレンドはわかりましたが、これからローソンストア100はどうなってしまうのでしょうか。ここからは、ローソングループが掲げている2030年に向けた具体的な目標数値と、そこから見えてくる「新しいローソンストア100」の姿について解説していきます。
今後の計画は330店への集約
驚かれるかもしれませんが、ローソンストア100は2030年までに店舗数を「330店」にするという目標を掲げています。現在の店舗数から考えると、約半分、あるいはそれ以上の規模まで縮小することになります。
これは単なる「撤退戦」ではなく、明確な意図を持った「戦略的縮小」です。これまでは店舗網を広げて面で戦う戦略でしたが、これからは「確実に利益が出せる精鋭部隊」だけで戦うスタイルにシフトチェンジしたと言えるでしょう。
閉店情報に見る整理対象店舗の基準
330店に絞り込まれる過程で、残念ながら閉店してしまう店舗も出てきます。どのような店舗が整理の対象になりやすいのか、その傾向を推測してみると、いくつかの基準が見えてきます。
- 競合(特に低価格スーパー)がすぐ近くにあり、価格競争で不利な店舗
- 賃料が高く、利益を圧迫している都心部の店舗
- 設備の老朽化が進み、改装コストが見合わない店舗
逆に言えば、これからのローソンストア100は、「競合が少なくて、地元のニーズにがっちりハマっている店舗」だけが残る形になりそうです。
メモ
近所のお店が改装されたり、新しい商品棚が入ったりしている場合は、今後も残る「勝ち残り店舗」である可能性が高いかもしれません。
新規出店を抑え高収益モデルへ転換
店舗数を減らす一方で、残った店舗には何が求められるのでしょうか。それは「高収益モデルへの転換」です。ただ安いものを売るだけでなく、多少値段が高くても買いたくなるような「付加価値」のある商品やサービスを提供する必要があります。
例えば、店内調理の温かいお弁当や、こだわりのデザートなど、100円均一の枠にとらわれない商品展開がカギになりそうです。数ではなく「質」で勝負する、新しいローソンストア100に期待したいですね。
2025年の既存店実績と課題
戦略転換の過渡期にある現在、店舗の数字はどうなっているのでしょうか。2025年3月のデータを見ると、課題と希望の両方が見え隠れしています。
先ほどお伝えした通り、客数は前年比94.6%と苦戦しています。しかし一方で、客単価は102.9%とアップしているんです。これは、お客さんの数は減ったけれど、一人あたりが使う金額は増えていることを意味します。
値上げの影響もあるかと思いますが、高単価な商品が受け入れられ始めている兆候とも取れます。この「客単価アップ」の流れを維持しつつ、いかに客数の減少を食い止めるかが、330店体制に向けた最大の課題と言えるでしょう。
まとめ:ローソンストア100の店舗数戦略の行方

今回は「ローソンストア100 店舗数」をテーマに、現状の減少トレンドや2030年に向けた330店への集約戦略について解説してきました。競合であるまいばすけっと等の台頭により、拡大路線から「選択と集中」へと大きく舵を切ったことがお分かりいただけたかと思います。
店舗数が減ることは利用者として寂しいですが、それは生き残りをかけた前向きな変化でもあります。今後、あなたの街に残るローソンストア100は、より便利で魅力的なお店に進化していくはずです。これからの変化を楽しみに見守っていきましょう。
免責事項
本記事の数値や分析は、公開情報や一般的な傾向に基づいた推測を含みます。最新かつ正確な店舗情報や経営方針については、必ずローソンの公式サイト等をご確認ください。また、投資判断などの際は専門家にご相談されることをお勧めします。