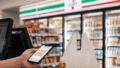肌寒くなってくると無性に恋しくなるのがセブンイレブンのおでんですね。お店に入った瞬間に漂うあの出汁の香りに誘われて、つい買ってしまうという方も多いのではないでしょうか。実はあのおでんのつゆは全国一律の味ではなく、北海道や関西など地域によって全く異なる出汁が使われていることをご存じでしたか。またご家庭で美味しいおでんを楽しみたいときや余ったつゆを活用したいときに、どのようなアレンジレシピがあるのかも気になるところです。カロリーや糖質を気にせず楽しめる具材の選び方も含めて、今回はセブンイレブンのおでんつゆに関する情報を詳しくまとめてみました。

- 地域ごとに異なるつゆの特徴と使用されている出汁の種類
- 旨味の相乗効果を生み出すこだわりの原材料と製法
- 家庭で簡単に再現できるおでんつゆのレシピとコツ
- 余ったつゆを活用した絶品の炊き込みご飯アレンジ
地域で味が違うセブンイレブンのおでんつゆ

セブンイレブンのおでんといえば、全国どこで食べても美味しいイメージがありますが、実はその地域ごとの食文化に合わせて、つゆの味が驚くほど細かく調整されているんです。ここでは、進化し続けるつゆのこだわりや、具体的な地域ごとの違いについて深掘りしていきましょう。
2024年の販売期間はいつから開始
まだまだ暑さが残る時期でも、コンビニのレジ横におでんが並んでいるのを見かけることがありますよね。実はセブンイレブンのおでんは、真冬だけでなく、8月下旬から9月にかけて販売が開始されることが多いんです。
これは、夏の暑さがピークを過ぎて朝晩の気温が少し下がり始めたころに、私たちが生理的に「温かい汁物」を欲するようになるタイミングに合わせているそうです。2024年のシーズンも、9月30日ごろから順次本格的な展開が始まり、「おでん6個購入でドリンク1本無料」といったお得なセールも行われていました。
ちなみに、この時期はまだ気温が高いため、店舗に入った瞬間に香る「かつお出汁の香り」が、私たちに季節の変わり目を感じさせる重要な役割を果たしているんですよ。
北海道など全国8種類の味の違い一覧
セブンイレブンのおでんつゆは、かつては7地域に分かれていましたが、現在ではさらに細分化され、なんと全国を8つの地域に分けて味を変えているそうです。旅行先で食べてみて「あれ?いつもと味が違う!」と感じたことがある方もいるかもしれませんが、それは気のせいではなかったんですね。
各地域のつゆの特徴を分かりやすく表にまとめてみました。
| 地域 | ベースとなる出汁 | 味の特徴 |
|---|---|---|
| 北海道 | 昆布 + 魚介出汁 | 海産資源を活かした魚介ベース。甘みと塩味のバランスが良い。 |
| 東北・信越 | 煮干し(焼き干し) | 焼き干しの香ばしさと力強い出汁感。塩分は少し高め。 |
| 関東 | かつお節 + 焼き干し | 濃口醤油を使用。かつおの酸味と香ばしさが際立つキレのある味。 |
| 東海 | むろあじ節 + 宗田鰹 | 「むろあじ節」特有の甘みと香り。味噌文化に負けないパンチのあるコク。 |
| 関西・北陸 | 昆布 + 鶏 | 薄口醤油で淡麗な見た目だが、鶏の旨味で濃厚なコクを表現。 |
| 中国 | 煮干し + 牛 | 瀬戸内の小魚に「牛」の旨味をプラス。複雑な甘みとコク。 |
| 四国 | 煮干し + 牛・鶏 | 煮干しと畜肉系の旨味に加え、甘味を強めに調整。 |
| 九州 | あご(トビウオ) + 鶏 | 特産の「あごだし」と鶏を使用。甘い醤油に合わせた濃厚な味。 |
こうして見ると、関東の「かつお」ベースや関西の「昆布」ベースだけでなく、中国地方で「牛」が使われていたり、九州で「あごだし」が使われていたりと、その土地ごとのソウルフードのような味わいを再現していることがよく分かります。
昆布と鰹節が作り出す旨味成分の秘密
なぜセブンイレブンのおでんつゆは、あんなにも奥深い味がするのでしょうか。その秘密は、単一の出汁ではなく、複数の素材を組み合わせることで生まれる「旨味の相乗効果」にあります。
基本となるのは以下の3つの要素です。
- 北海道産日高昆布(グルタミン酸):植物性の旨味のベース。煮崩れしにくく、クセのないコクを出します。
- 枕崎産かつお節(イノシン酸):動物性の旨味。「手火山式」などの焙乾法で、燻製のような香ばしい香りを付加しています。
- 煮干し(イノシン酸・ミネラル):魚介の力強い旨味と味の輪郭を作ります。
昆布の「グルタミン酸」と、かつおや煮干しの「イノシン酸」を組み合わせると、旨味が飛躍的に強くなることが科学的にも証明されています。これが、私たちが「美味しい」と感じる決定的な理由なんです。
気になる具材のカロリーと糖質の情報
寒い時期にはついつい食べ過ぎてしまうおでんですが、ダイエット中の方にとってはカロリーや糖質も気になりますよね。2025年に向けて健康志向が高まる中、おでんは選び方次第で非常に優秀なダイエット食になります。
まず、大根、こんにゃく、白滝といった定番具材は、1個あたり数kcal~十数kcal程度と非常に低カロリーです。これらを中心に選べば、満腹感を得ながら摂取カロリーを抑えることができます。
注意したいのは「もち巾着」や「ちくわぶ」、一部の練り物です。これらは炭水化物が多く含まれるため、糖質が高くなる傾向があります。
一方で、最近リニューアルされた「厚揚げ」などはおすすめです。豆腐の濃度を上げてコクが増しており、低糖質ながら良質なタンパク質と植物性脂質が摂れるため、満足感も高いですよ。
市販のおでんの素は販売されているか
「このセブンの味を家でも手軽に楽しみたい」という方向けに、実はセブン&アイグループのプライベートブランド「セブンプレミアム」から、「おでんの素」が販売されています。
顆粒タイプだけでなく、液体濃縮タイプや小分けパックなどがあり、パッケージにはしっかりと「日高昆布・枕崎産かつお節使用」と書かれています。これを使えば、一から出汁を取らなくても、お店の味に近いクオリティを家庭で再現できるので非常に便利です。おでんだけでなく、煮物や鍋のベースとしても使える汎用性の高さも魅力ですね。
家庭で作るセブンイレブンのおでんつゆの再現

市販の素を使うのも良いですが、キッチンにある調味料を使って、自分好みにアレンジしながら「セブン風」の味を作れたら楽しいですよね。ここからは、SNSや口コミサイトでも話題になっている再現レシピや、余ったつゆを最後まで楽しみ尽くす方法をご紹介します。
白だしで簡単にする人気の再現レシピ
一から鰹節と昆布で出汁を取るのは大変ですが、市販の「白だし」を使えば、かなり近い味を再現することができます。セブンイレブンのつゆのような、透き通っていて雑味のない味を目指すなら、以下のポイントを意識してみてください。
スクラッチ派(手作り派)の方に試してほしいのが、大根の下茹でに「米のとぎ汁」を使うことです。これは本格的な和食の技法ですが、大根の臭みやえぐみが抜け、味が染み込みやすくなります。
味付けは「白だし」をベースに、少量の塩と薄口醤油で調整するのがコツです。色が濃くなりすぎないように醤油は控えめにし、塩で味を決めると、お店のような上品な仕上がりになりますよ。
濃厚な味噌だれで楽しむ名古屋風の味
東海地方の味、いわゆる「味噌おでん」がお好きな方は、通常のつゆだけでは物足りないかもしれません。そんなときは、基本の和風出汁にアレンジを加える「ちょい足し」がおすすめです。
標準的なおでんつゆをベースにしつつ、そこに赤味噌(八丁味噌など)と砂糖をたっぷりと溶かし入れます。甘辛く濃厚な味噌だれにすることで、大根や牛すじ、卵といった具材が全く違った表情を見せてくれます。これは地域性を家庭で楽しむ醍醐味ですね。
余ったつゆで作る絶品炊き込みご飯
おでんを食べ終わった後、旨味がたっぷりと溶け出したつゆを捨ててしまうのはもったいないですよね。実はこの「残りつゆ」は、最強の炊き込みご飯の素になるんです。
具材(練り物や根菜など)からも出汁が出ているため、複雑で濃厚な味わいになっています。作り方は簡単で、いつもの水加減の代わりにおでんのつゆを使い、余った具材を細かく刻んで一緒に炊くだけです。
一度煮込まれて味が染みた具材を炊き込むことで、ご飯全体に旨味が還流し、奥深い味わいになります。これはフードロス削減にもつながる、賢くて美味しい活用術です。
公式推奨のごま油を使ったアレンジ
さらに炊き込みご飯を美味しくするための「黄金比」をご存じでしょうか。セブンプレミアムの公式レシピでも推奨されている方法があり、それが調味料と「ごま油」の追加です。
米2合に対して、以下の割合を目安にしてみてください。
- 醤油:小さじ5
- みりん:小さじ3
- ごま油:小さじ2
ポイントは「ごま油」です。和風の出汁にごま油を加えることで、お米一粒一粒が油分でコーティングされ、炊き上がりがツヤツヤになります。また、魚介特有の匂いをマスキングしつつ、冷めても美味しいコクのある仕上がりになるので、おにぎりにして翌日のランチにするのも最高ですよ。
まとめで振り返るセブンイレブンのおでんのつゆ

今回は、セブンイレブンのおでんつゆのこだわりの世界についてご紹介しました。全国8地域に分かれた緻密な味の設計や、昆布と鰹節による旨味の相乗効果など、たかがコンビニのおでんと侮れない工夫が詰まっていましたね。
お店でそれぞれの地域の味を楽しんだり、ご家庭で白だしやごま油を使って再現・アレンジを楽しんだりと、おでんの楽しみ方は無限大です。ぜひ今夜は、温かいおでんで心も体も満たされてみてはいかがでしょうか。
※本記事で紹介した情報は一般的な傾向や過去のデータを基にしています。地域や時期によって商品の仕様が異なる場合がありますので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。