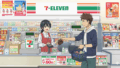日本のコンビニエンスストアの基盤を築いたとも考えられるセブン-イレブン・ジャパン。その発祥から一号店の開店、そして今日に至るまで、数多くの歴代社長たちが会社を導いてきました。社長が交代する背景にはどのような物語があったのか、また各々に求められた経営の能力とは何だったのでしょうか。そして現在の役員や取締役の体制、さらには親会社における初の外人CEOの就任など、気になる点は多いかもしれません。この記事では、セブンイレブンの会社概要にも触れながら、セブンイレブン社長の歴代の変遷を詳しく解説します。
- セブン-イレブンの創業期から現在までの歴代社長の変遷
- 各社長の経歴や在任期間中の主な功績
- 社長交代の背景や企業の成長戦略
- 現在の役員体制と今後の展望
セブンイレブン社長の歴代を知るための基礎知識

- セブンイレブンの発祥はアメリカ
- 日本の一号店は豊洲から始まった
- セブン-イレブン・ジャパンの設立
- 現在のセブンイレブンの会社概要
セブンイレブンの発祥はアメリカ
今や日本全国に店舗を構えるセブン-イレブンですが、そのルーツはアメリカにあります。1927年、テキサス州オーククリフで氷販売店を営んでいたサウスランド・アイス社が、顧客の要望に応えてパンや牛乳、卵といった日用品を置き始めたのが始まりです。当初は「トーテム・ストア」という名前でしたが、後に営業時間を朝7時から夜11時までに拡大したことから、1946年に「セブン-イレブン」へと改称されました。
このビジネスモデルがコンビニエンスストアの原型となり、アメリカでフランチャイズ展開を進めていきました。日本でセブン-イレブンが誕生する約半世紀も前に、すでにその基礎が築かれていたことになります。日本での独自の発展の前に、アメリカでの長い歴史が存在する点は、企業を理解する上で大切な背景と言えるでしょう。
日本の一号店は豊洲から始まった
日本におけるセブン-イレブンの歴史は、1974年5月15日に東京都江東区豊洲にオープンした「豊洲店」から始まりました。この記念すべき一号店は、もともと「山本茂商店」という酒屋を経営していた山本憲司氏が、酒屋の将来性に疑問を感じ、新しいビジネスモデルであったセブン-イレブンのフランチャイズに応募したことで実現しました。
開店当日、最初に売れた商品はサングラスであったという逸話は、今でも語り継がれています。当時、コンビニエンスストアという業態自体が珍しかったため、何が売れるか手探りの状態でした。しかし、この一号店の成功が、その後の爆発的な店舗展開の礎を築いたことは間違いありません。ちなみに、この豊洲店は建て替えを経て、現在も同じ場所で営業を続けています。
セブン-イレブン・ジャパンの設立
セブン-イレブン・ジャパンは、1973年11月20日に「株式会社ヨークセブン」として設立されたのが始まりです。当時、総合スーパー「イトーヨーカドー」が、アメリカのサウスランド社とライセンス契約を結び、日本でのコンビニエンスストア事業を開始しました。
この新規事業を推進したのは、後にセブン&アイ・ホールディングスの「総帥」として知られることになる鈴木敏文氏です。当時、イトーヨーカドー社内では日本の商習慣に合わないとして懐疑的な声が多かったものの、鈴木氏はその将来性を確信していました。そして、もし事業が失敗した場合は自身のイトーヨーカドー株で補填するという覚悟で、創業者である伊藤雅俊氏の了解を取り付けたと言われています。この強い意志がなければ、現在のセブン-イレブンは存在しなかったかもしれません。
現在のセブンイレブンの会社概要
ここでは、株式会社セブン-イレブン・ジャパンの現在の基本的な企業情報をご紹介します。国内外に広がる広大なネットワークと、日本の小売業界におけるその立ち位置を、以下の表から確認できます。
| 項目 | 内容 |
| 正式社名 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
| 本社所在地 | 東京都千代田区二番町8番地8 |
| 設立年月日 | 1973年(昭和48年)11月20日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 阿久津 知洋 |
| 資本金 | 172億円 |
| 国内店舗数 | 21,563店(2025年8月末時点) |
| 親会社 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
セブンイレブン社長の歴代と現在の経営陣
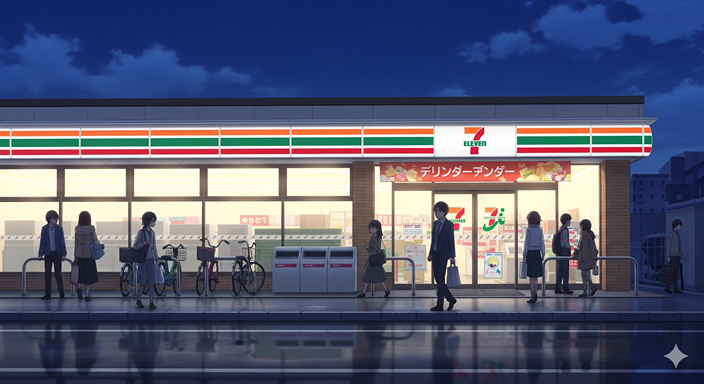
- セブンイレブンジャパンの歴代社長一覧
- 近年の社長交代とその背景
- 親会社セブン&アイHDの取締役
- ジャパン社の現在の役員体制
- 親会社に初の外人CEOが就任
- 歴代社長に求められた経営能力
- セブンイレブン社長の歴代から見る経営の変遷
セブンイレブンジャパンの歴代社長一覧
株式会社セブン-イレブン・ジャパン(旧:株式会社ヨークセブン)の設立から現在までの歴代社長は以下の通りです。創業者から現在の経営陣に至るまで、それぞれの時代で会社を牽引してきました。
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 主な役職・功績など |
| 初代 | 伊藤 雅俊 | 1973年 – 1978年 | イトーヨーカ堂創業者。日本でのセブン-イレブン事業を開始 |
| 2代 | 鈴木 敏文 | 1978年 – 1992年 | 日本型コンビニモデルの確立者。POSシステム導入などを推進 |
| 3代 | 栗田 裕夫 | 1992年 – 1997年 | 陸上自衛隊出身。安定成長期を支える |
| 4代 | 工藤 健 | 1997年 – 2002年 | 5,000店舗から10,000店舗への拡大期を牽引 |
| 5代 | 山口 俊郎 | 2002年 – 2009年 | アイワイバンク銀行(現セブン銀行)設立など金融サービスを強化 |
| 6代 | 井阪 隆一 | 2009年 – 2016年 | セブンプレミアムの開発を主導。後にセブン&アイHD社長へ |
| 7代 | 古屋 一樹 | 2016年 – 2019年 | 47都道府県への出店達成を推進 |
| 8代 | 永松 文彦 | 2019年 – 2025年 | 加盟店との関係改善やDX推進に取り組む |
| 9代 | 阿久津 知洋 | 2025年 – 現職 | 商品開発部門出身。顧客ニーズへの対応力強化を目指す |
近年の社長交代とその背景
セブン-イレブン・ジャパンでは、市場環境の変化や経営課題に対応するため、近年も社長交代が行われています。特に注目されたのが、2025年3月1日付で永松文彦氏から阿久津知洋氏へと社長が交代した人事です。
永松氏は、人手不足を背景とした24時間営業問題や加盟店との関係性など、難しい課題に直面した時期のトップでした。在任中は、加盟店支援の強化や店舗の省人化、DX(デジタル変革)の推進など、構造改革に取り組みました。
一方、後任の阿久津氏は、長年にわたり商品開発部門を歩んできた人物です。この交代の背景には、プライベートブランド商品のさらなる強化や、多様化する顧客ニーズに迅速に対応できる商品力を武器に、競争が激化する小売業界での優位性を改めて確立したいという経営陣の狙いがあると考えられます。原材料価格の高騰といった課題に対し、商品開発の専門家をトップに据えることで、難局を乗り越えようとする意志の表れと見ることができます。
親会社セブン&アイHDの取締役
セブン-イレブン・ジャパンの親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、グループ全体の経営戦略を決定する重要な役割を担っています。そのため、取締役会の構成はグループの方向性を知る上で非常に参考になります。
2025年7月時点の公式情報によると、取締役会は社内出身の取締役に加え、多様なバックグラウンドを持つ社外取締役で構成されています。例えば、他の大手企業の経営経験者や法律、金融の専門家などが名を連ねています。
このような構成は、経営の透明性を高め、客観的な視点を取り入れる「コーポレート・ガバナンス」を強化する目的があります。社外取締役は、経営陣に対して独立した立場から助言や監督を行うことで、企業価値の向上を図る役割が期待されています。セブン&アイ・ホールディングスがグローバルな競争環境で勝ち抜くために、多角的な視点を持つ取締役会が不可欠であると言えるでしょう。
ジャパン社の現在の役員体制
株式会社セブン-イレブン・ジャパンの経営は、社長だけでなく、各部門を統括する役員たちによって支えられています。現在の役員体制を見ると、会社の重点領域をうかがい知ることが可能です。
代表取締役社長の阿久津知洋氏のもと、店舗運営、商品開発、物流、システム、人事、財務といった各機能に専門の執行役員が配置されています。特に、阿久津氏自身が商品開発のエキスパートであることから、商品本部の役割はこれまで以上に大きくなっていると考えられます。
また、近年ではDX(デジタル変革)やサステナビリティ(持続可能性)といった分野も企業の成長に欠かせない要素となっています。そのため、これらの領域を専門とする役員を配置し、組織横断的に取り組みを進める体制が構築されているのが特徴です。現場のオペレーションを支える役員から、未来の成長戦略を描く役員まで、バランスの取れた布陣で経営にあたっていると言えます。
親会社に初の外人CEOが就任
セブン&アイ・ホールディングスの経営体制において、特筆すべきはスティーブン・ヘイズ・デイカス氏が代表取締役社長CEO(最高経営責任者)を務めている点です。これは、同社にとって初の外国人トップとなります。
デイカス氏は、カナダのコンビニ大手「アリマンタシオン・クシュタール」の元幹部であり、グローバルな小売業界で豊富な経験を持っています。彼の就任は、セブン&アイグループが国内市場だけでなく、海外事業、特に北米でのコンビニ事業を成長の柱としてさらに強化していくという強いメッセージと受け取れます。
日本の伝統的な大企業で外国人トップが就任する例はまだ多くはありません。この人事は、同社が国籍にとらわれず、グローバルな視点と経営能力を持つ人材を登用することで、持続的な成長を目指す姿勢を示しています。国内事業とのシナジーをいかに生み出していくか、その手腕が注目されます。
歴代社長に求められた経営能力
セブン-イレブン・ジャパンの歴代社長に求められてきた経営能力は、時代と共に変化してきました。
創業期から成長期(伊藤雅俊氏、鈴木敏文氏)
創業期の伊藤雅俊氏や、日本型コンビニモデルを確立した鈴木敏文氏の時代には、何よりも「構想力」と「実行力」が求められました。まだ日本に存在しなかったビジネスモデルを導入し、メーカーを巻き込んだ共同配送やPOSシステムの導入といった、業界の常識を覆す仕組みを次々と構築する力が必要でした。
安定・拡大期(栗田氏〜井阪氏)
事業が軌道に乗り、店舗網が拡大していく安定期には、既存のビジネスモデルを磨き上げ、組織を効率的に運営する「管理能力」や「調整力」が重要になりました。フランチャイズ加盟店との良好な関係を維持しつつ、セブンプレミアムのような新たな価値を創出する力が鍵となりました。
変革期(古屋氏〜現在)
そして、市場が飽和し、社会構造が変化する現代においては、既存の成功体験にとらわれず、ビジネスモデル自体を変革していく「改革力」が不可欠です。24時間営業問題への対応、DXの推進、そして海外事業との連携強化など、過去にない課題に対応する柔軟な思考とリーダーシップが、現在の経営トップには求められています。
セブンイレブン社長の歴代から見る経営の変遷

この記事で解説したセブン-イレブン・ジャパンの歴代社長に関する情報を、最後に要点としてまとめます。
- セブン-イレブンの発祥は1927年のアメリカ・テキサス州
- 氷販売店だったサウスランド・アイス社が前身
- 日本での事業はイトーヨーカドーがライセンス契約を結び開始
- 1973年に株式会社ヨークセブンとして設立
- 日本の第一号店は1974年に開店した豊洲店
- 初代社長はイトーヨーカ堂創業者の伊藤雅俊氏
- 2代目社長の鈴木敏文氏が日本型コンビニモデルを確立
- POSシステム導入や共同配送など画期的な仕組みを構築
- 歴代社長は時代の要請に応じて異なる経営能力を発揮
- 創業期は構想力、成長期は管理能力、現代は改革力が求められる
- 2025年に永松文彦氏から阿久津知洋氏へ社長が交代
- 阿久津氏は商品開発部門出身で商品力強化が期待される
- 親会社のセブン&アイHDは初の外国人CEOであるデイカス氏がトップ
- グローバル展開と経営の透明性強化が現在の課題
- 取締役会は多様な専門性を持つ社外取締役で構成される