「セブンイレブンはどこの国の企業?」そう考えたことはありませんか。街の至る所で見かけるこのコンビニですが、そのルーツを辿ると、実は壮大な物語が隠されています。セブンイレブンの元祖はアメリカにありますが、紆余曲折を経て、日本の企業がその本社を買収したという驚きの歴史があるのです。現在、日本国内ではローソンやファミリーマートとしのぎを削る一方、世界に目を向けると、店舗が最も多い国は意外な場所かもしれません。この記事では、「セブンイレブンはどこの国?」という素朴な疑問の答えから、記念すべき日本一号店の誕生秘話、さらには小顔効果が期待できるコスメの話題まで、その多角的な魅力を徹底的に掘り下げていきます。
この記事を読むことで、以下の点について深く理解できます。
- セブンイレブンの発祥国と日本での始まり
- アメリカ本社を買収した驚きの歴史的背景
- 世界のどの国に店舗が多いのかというグローバルな展開状況
- 日本における主要な競合他社との関係性や戦略の違い
セブンイレブンはどこの国が始まり?元祖と日本の歴史

- 元祖はアメリカの氷販売店から
- コンビニの歴史はアメリカで誕生
- 日本での展開と独自の進化
- 記念すべき日本の日本一号店
- 経営危機に陥ったアメリカの本社
- 日本が親会社を劇的に買収
元祖はアメリカの氷販売店から
セブンイレブンの物語は、1927年のアメリカ・テキサス州ダラスで、一軒の氷販売店から始まりました。サウスランド・アイス・カンパニーという名のこの会社は、当時まだ電気冷蔵庫が普及していなかった時代に、人々の生活に不可欠な氷を販売していました。
ある時、店舗を任されていた一人の従業員が、来店客からの「氷だけでなく、パンや牛乳、卵も一緒に買えたら便利なのに」という声に耳を傾けます。彼は自腹でこれらの食料品を仕入れて販売したところ、これが大好評となりました。顧客の「あったらいいな」に応えるこの小さな試みが、世界初のコンビニエンスストアの原型となったのです。
当初、この便利なお店は、目印として店舗の前に建てられたトーテムポールにちなんで「トーテム・ストア」と呼ばれていました。顧客のニーズを的確に捉え、それに応えるという姿勢は、この時からセブンイレブンの根幹をなす理念となっています。
コンビニの歴史はアメリカで誕生
前述の通り、コンビニエンスストアの歴史はアメリカで幕を開けました。「トーテム・ストア」は、お客様の利便性を追求する中で、徐々にその形を進化させていきます。
1946年、戦後の復興期に入ると、営業時間を当時の小売店としては異例の「朝7時から夜11時まで」に拡大しました。この画期的な営業時間にちなんで、店名を「7-Eleven(セブン-イレブン)」へと変更したのです。この名前は、今では世界中で知られるブランド名の由来となりました。
さらに1960年代には、テキサス州のある店舗が、大学フットボールの試合後に集まる学生たちのために夜通し店を開けたことをきっかけに、24時間営業の実験を開始します。これもまた顧客の要望に応えた結果であり、コンビニエンスストアの利便性を象エン徴するサービスとして定着していきました。このように、アメリカで生まれたセブン-イレブンは、常にお客様の声を聞き、時代の変化に対応しながら成長を続けたのです。
日本での展開と独自の進化
アメリカで誕生したセブン-イレブンですが、日本に渡ってからそのビジネスモデルは独自の進化を遂げることになります。1973年、当時スーパーマーケットを運営していたイトーヨーカドーが、新規事業としてコンビニエンスストアに着目しました。創業者である鈴木敏文氏は、アメリカでセブン-イレブンと出会い、その将来性を確信して日本での展開を決意します。
こうして株式会社ヨークセブン(後のセブン-イレブン・ジャパン)が設立されましたが、当初はアメリカの仕組みをそのまま導入しても、日本の商習慣や食文化には合わない部分が多くありました。そこで日本独自の徹底したローカライズが進められます。
代表的なものが、今ではコンビニの定番である「おにぎり」や「弁当」の本格的な販売です。食品メーカーと共同で商品を開発する「チームMD」という手法を取り入れ、次々とヒット商品を生み出しました。また、どの商品がいつ、どれだけ売れたかを単品ごとに管理する「単品管理」や、複数のメーカーの商品をまとめて配送する「共同配送」といった革新的なシステムを構築。これにより、品切れや売れ残りを最小限に抑え、常に新鮮な商品を顧客に提供できる高効率な経営を実現しました。これらの取り組みが、日本のセブン-イレブンを飛躍的に成長させる原動力となったのです。
記念すべき日本の日本一号店
日本のコンビニエンスストアの歴史を語る上で欠かせないのが、セブン-イレブン日本一号店の誕生です。1974年5月15日、東京都江東区豊洲に「セブン-イレブン豊洲店」がオープンしました。これは、日本初の本格的なフランチャイズシステムによるコンビニエンスストアの開店でもありました。
元々は酒屋だった店舗が、新しい業態へと挑戦した形です。開店当初、一番最初に売れた商品は、意外にもサングラスだったという逸話が残っています。当時、コンビニという業態自体が目新しく、多くの人々が期待と好奇の目でこの新しい店の門出を見守っていました。
この豊洲店を皮切りに、セブン-イレブンは特定の地域に集中的に出店する「ドミナント戦略」を展開。物流や広告の効率を高めながら、着実に店舗網を拡大していきました。記念すべき日本一号店は、その後の日本のライフスタイルを大きく変えることになるコンビニ文化の、まさに始まりの場所だったと言えます。
経営危機に陥ったアメリカの本社
日本のセブン-イレブンが順調に店舗数を増やし、独自の進化を遂げていた1980年代後半、生みの親であるアメリカ本社のサウスランド・コーポレーションは、深刻な経営危機に直面していました。
その原因は複合的でした。一つは、本業であるコンビニ事業との相乗効果を狙って行った多角化の失敗です。買収した石油精製事業が原油価格の暴落で巨額の損失を生み、不動産開発事業も市況の悪化で不振に陥りました。
もう一つの大きな要因は、敵対的買収から会社を守るために行ったMBO(経営陣による買収)です。これにより多額の負債を抱え込むことになり、財務状況は急速に悪化しました。さらに、店舗は薄暗く、商品の鮮度管理も行き届いていないなど、小売業としての基本的な魅力も失われつつありました。かつての輝きを失ったアメリカのセブン-イレブンは、1991年、ついに連邦破産法11条の適用を申請する事態に至ります。
日本が親会社を劇的に買収
アメリカ本社の経営破綻という未曾有の危機に際し、救いの手を差し伸べたのが、皮肉にも「弟子」である日本のセブン-イレブンと親会社のイトーヨーカ堂でした。1991年、両社は共同で約4億3000万ドルを出資し、経営危機に陥っていたサウスランド社の株式の約7割を取得。これにより、子が親を救うという世界でも類を見ない劇的な買収が成立しました。
この買収は、単なる資金援助にとどまりませんでした。日本側は、経営再建のために自らが培ってきた独自のノウハウを惜しみなく投入します。特に重要だったのが、「単品管理」の導入です。商品一つひとつの販売データを徹底的に分析し、仮説と検証を繰り返して発注精度を高めるこの手法は、メーカー主導の仕入れが常態化していたアメリカの店舗に大きな変革をもたらしました。
最初は文化の違いから大きな反発があったものの、粘り強く改革を断行。店舗の改装や照明の改善、ディスカウント販売の廃止といった基本に忠実な施策も同時に進めました。これらの取り組みが功を奏し、業績はV字回復。再建からわずか3年で黒字転換を達成し、2000年にはニューヨーク証券取引所への再上場を果たしたのです。
世界のセブンイレブンはどこの国に展開?店舗数と競合
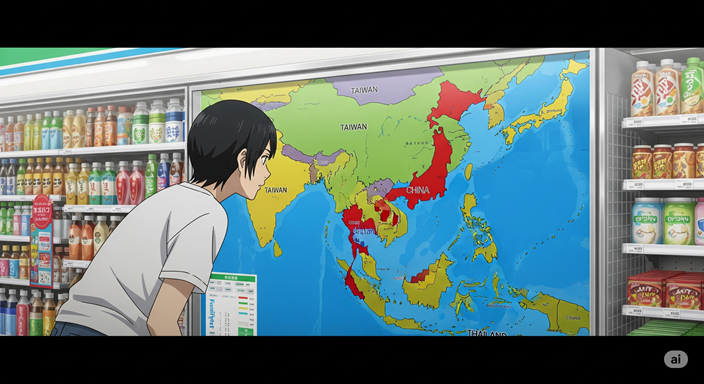
- 店舗数が圧倒的に多い国はどこ?
- ファミリーマートとの海外戦略比較
- ローソンとの国内・海外戦略の違い
- まとめ:セブンイレブンはどこの国でも進化を続ける
店舗数が圧倒的に多い国はどこ?
セブン-イレブンは今や世界的なコンビニエンスストアチェーンであり、その店舗は多くの国と地域に広がっています。では、店舗数が圧倒的に多い国はどこなのでしょうか。
答えは日本です。2024年時点の情報によると、全世界に存在する約85,000店のセブン-イレブンのうち、日本国内には21,000店以上が存在し、国別で見ると断トツの1位となっています。
日本に次いで店舗数が多いのは、タイで、約11,000店を超えています。タイではセブン-イレブンが生活に深く根付いており、独自の食品やサービスが観光客からも人気を集めています。3位は韓国、4位は発祥の地であるアメリカと続きます。
このように、セブン-イレブンはもともとアメリカで生まれましたが、日本で大きく成長し、今では日本が世界最大の店舗数を誇る中心的な市場となっていることが分かります。
| 順位 | 国・地域 | 推定店舗数(2024年時点) |
| 1 | 日本 | 約21,500店 |
| 2 | タイ | 約11,300店 |
| 3 | 韓国 | 約9,500店 |
| 4 | アメリカ | 約9,000店 |
| 5 | 台湾 | 約5,500店 |
※上記店舗数は公表データや報道に基づく推定値であり、常に変動します。
ファミリーマートとの海外戦略比較
日本国内でセブン-イレブンと激しい競争を繰り広げるファミリーマートも、早くから海外展開に積極的な企業の一つです。両社の海外戦略には、いくつかの違いが見られます。
ファミリーマートは、1988年に台湾へ進出したのを皮切りに、主にアジア地域を中心とした海外展開を進めてきました。特に台湾、中国、タイなどで多くの店舗を運営しています。一時はアメリカにも進出しましたが、2015年に撤退しており、現在はアジア市場に経営資源を集中させる戦略をとっていると考えられます。
一方、セブン-イレブンは、日本法人がアメリカ本社を買収した経緯から、北米市場で強力な基盤を持っています。これに加えて、アジア各国やオーストラリア、さらには北欧にも店舗を展開しており、ファミリーマートより広範囲なグローバル展開が特徴です。
また、展開方法にも違いがあります。セブン-イレブンは、現地の有力企業にライセンスを供与し、ブランド運営を任せる「エリアライセンシー契約」を積極的に活用しています。これにより、各地域の市場に精通したパートナーの力を借りて、スピーディーな店舗網拡大を可能にしています。ファミリーマートも合弁事業などを活用しますが、セブン-イレブンほどエリアライセンシー契約に依存していない点が異なります。
ローソンとの国内・海外戦略の違い
国内コンビニ業界で3位のローソンもまた、セブン-イレブンとは異なる戦略で国内外の市場に挑んでいます。
海外戦略において、ローソンは日系コンビニとしてはいち早く1996年に中国大陸へ進出しました。上海を中心に店舗を展開し、現地の食文化に合わせた「おでん」を広めるなど、市場の開拓者としての役割を果たしました。しかし、その後の展開ではセブン-イレブンやファミリーマートに店舗数で差をつけられており、近年は店舗数の拡大よりも、サービスの質向上やデジタル技術を活用した店舗運営の効率化に注力している様子がうかがえます。展開エリアも、現時点では中国と東南アジアの一部に限定されています。
国内での競争においては、ローソンは独自の強みで差別化を図っています。例えば、健康志向のプライベートブランド「ナチュラルローソン」や、店内調理サービス「まちかど厨房」、エンタメ分野に強い「ローソンチケット」など、特定の顧客層に響くユニークな商品・サービスを展開しています。
セブン-イレブンが圧倒的な店舗網と商品開発力を背景にマスマーケットを狙うのに対し、ローソンは特色あるサービスで特定のファンを掴む戦略をとっている点に、両社の国内戦略の大きな違いが見て取れます。
まとめ:セブンイレブンはどこの国でも進化を続ける

- セブンイレブンの元祖は1927年にアメリカで創業した氷販売店
- 当初の店名は目印のトーテムポールにちなんだ「トーテム・ストア」だった
- 「セブン-イレブン」という名前は朝7時から夜11時までの営業時間に由来する
- 日本での第一歩は1974年に開店した東京の豊洲店
- おにぎりや弁当の販売、単品管理、共同配送など日本独自の仕組みで大成功を収めた
- 1991年に日本のイトーヨーカ堂などが経営破綻したアメリカ本社を買収
- 現在、セブン-イレブンブランドを所有する本社機能は日本にあると言える
- 世界で最も店舗数が多い国は日本で、2万店以上を展開している
- 日本に次いでタイ、韓国、アメリカ、台湾の順で店舗が多い
- 海外では現地の有力企業に経営を任せるエリアライセンシー方式も活用
- 競合のファミリーマートはアジア中心、ローソンは中国や東南アジアに注力している
- 発祥の地アメリカの店舗も、日本のノウハウ導入によって再生を果たした
- コンビニの生みの親でありながら、日本の「弟子」に救われたというユニークな歴史を持つ
- 今や日本を代表するグローバルな小売企業の一つとして世界に展開
- セブンイレブンはこれからも、それぞれの国や地域のニーズに合わせて進化を続けていく

